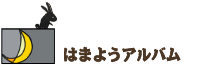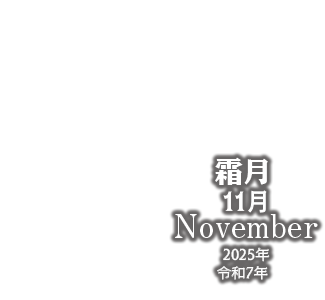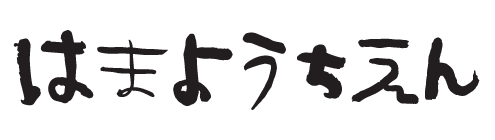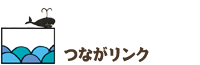|


ファンタジーが根っ子を育てる。
立冬を目前にして、ようやく金木犀の香りがどこからともなく漂ってきた11月4日。
朝登園してきた子どもたちは、
園庭に刻まれた複数の大きな足跡のような痕跡や
なぎ倒されたフェンスやビールケース、
散乱する緑色の繊維をみつけて大騒ぎ。
たちまち思い思いに気づいたことや
推測したことを話しあいます。
おそるおそる「なんか来たんじゃない?」と囁く(5歳児)。
「あしあと11個ある」とひらめきの観点を差し出す(5歳児)。
「恐竜の足やで」と得意げに断定する人(4歳児)に、
「恐竜は絶滅したからおれへんで」と知識で応答する(5歳児)。
理解を超えた事態の大きさにおののき
「きんきゅうじたいだー」と叫ぶ(3歳児)。
「あしの幅が大きい」 「大きい身体なのかな」 「ぞうかな?」
「がおがおって走っていったんかな?」と見たままの
気づきを思いつくままに声にする(3歳児)。
ケヤキの枝には大きな服のような布や封筒が
引っかかっているのを発見。
封筒のなかに入っていた手紙によると、
「ぐるりん」という「ぼく」が
「もり」がゴミだらけになり、
食べるものがなくなった窮状を訴える内容でした。
それを知った子どもたちは、
森がゴミまみれになったのは
「ごみばこがないから?」と推測したり、
最近の熊出没の情報を思いだし
「食べものがなくなったからやってきた」と分析したり、
手紙に記された図柄を
「リサイクルマークや」と連想したりと、
目の前に起きた事実を現実世界の出来事にリンクさせ、
自分の知識や経験をもとに気づいたことや
感じたことを話しあいました。
 こうした言葉のやりとりを通して
こうした言葉のやりとりを通して想像力の思考回路が開き、
ファンタジーと現実の境は溶け、
子どもたちの感性の冒険が幕を開けるのです。
私たちは、このファンタジーの仕掛けを、
単なる子供騙しの“ごっこ遊び”と見ていません。
子どもたちは、現実として見えるものと
見えないものとの境を行き来しながら、
「なぜだろう」「どうして」「だとすれば」
「どうすればいい」と思考を巡らし、
自分たちなりの答えを探す
“探求の旅人”となるのです。
そこには、未来を生きる子どもたちにこそ必要な、
思考の種が詰まっています。
この種には、仮説を立てることや
批判的に思考すること、
他者の立場に立てるようになる成分を含み、
自分たちで問題を解決し
世界を変えることができるという
萌芽を生み出します。
この学びは、大人になってからも生涯
消えることの無い「生きぬく力」を、
彼らに授けてくれると私たちは信じています。
目に見えることがすべて。
結果が予測可能な場合にのみ行動する。
ひとつの答えを求め続ける。
信じられるのは現実だけ。
そういった思考や行動の先にあるのは、
深い森のなかに迷い込むような
行き止まりです。
ファンタジーは、暗い森に差しこむ希望の光のように、
物語とともにいた人にだけ、次に選ぶべき道を
そっと照らしてくれます。
「わたしになる。ぼくになる。」
その根っ子を育てるために必要なのは、
答えを急がず、問いを手放さずにいられる時間。
予測不能なこれからの世界を生きる子どもたちにとって、
これこそが今しか育めない、
かけがえのない学びだと信じるはまようです。

| 日 | 曜日 | 行事 | 降園時刻 |
|---|---|---|---|
| 4 | 火 | (再)卒園アルバム用かぞく写真撮影 | 14:00 |
| 5 7 |
火 金 |
ファンタジープロジェクト参観 | 14:00 |
| 9 | 日 | 親子ハイキング | - |
| 18 | 火 | 子育てあのね | 14:00 |
| 22 | 土 | ファンタジープロジェクト親子鑑賞日 | - |
| 26 | 水 | 11月うまれのおたんじょうかい | 14:00 |
| 29 | 土 | OPENDAY | - |
| 30 | 日 | うえださんの畑へ行こう | - |
| 日 | 曜日 | 行事 |
|---|---|---|
| 8 | 土 | かぞく懇談 |
| 18 | 水 | 子育てあのね |
| 29 | 土 | OPENDAY |
| 30 | 日 | うえださんの畑へ行こう |